パソコンやケータイ、ゲーム機器のなどの使用により子供を中心に増えている近視。
ある調査によれば、2050年には世界の約半数がかかる可能性があるともいわれています。
現在は、メガネやコンタクトレンズ、レーシックなどによる矯正が知られていますが、『窪田製薬ホールディングス』がかけるだけで近視を治療できる『クボタメガネ』を開発しました。
Contents
近眼はなぜ起こる?
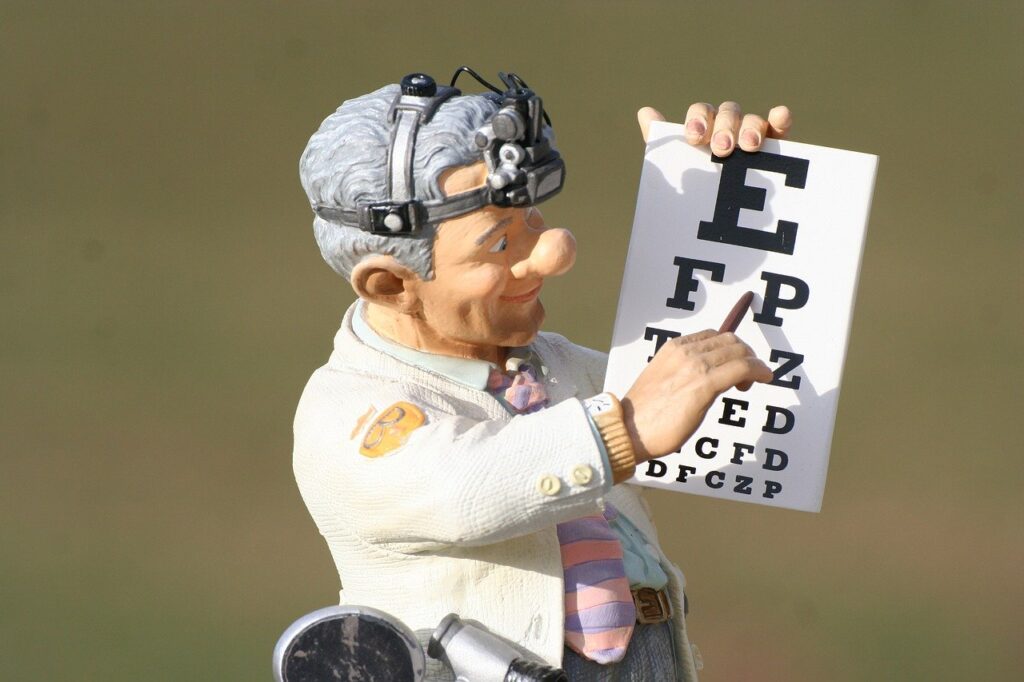
私たちの眼の仕組みは、言い換えればカメラの構造と似ています。
カメラのレンズに相当するのが角膜と水晶体です。
正常な状態であれば、眼と見る物との距離により角膜や水晶体が屈折力を調節し、網膜上でちょうどピントが合う状態になります。
近視の場合は、角膜や水晶体の屈折力が強すぎて網膜の手前でピントが合ってしまう状態のことです。
そうなってしまうと、近くのものはよく見えるものの、遠くのものはぼんやりとしか見えない、といった症状が生じます。
例えば、近くで読む本がよく読む本がはっきりと見えるのに、そのまま遠くの看板を見たりするとぼんやりとしか見えない、という状態となります。
近視の種類には軸性近視と屈折性近視の2つがあります。
屈折性近視 ⇒ 角膜と水晶体の長さの眼球の長さを眼軸といいます。この長さが正常な状態より長くなるとこの眼軸が長すぎると、網膜より手前で画像のピントが合ってしまい、遠くのものが見えにく状態になります。
大部分の近視がこの軸性近視に該当します。
軸性近視 ⇒ 角膜と網膜とを結ぶ線を眼軸と言いますが、その眼軸が長すぎると網膜の手前でピントとが合ってしまい、遠くのものが見えにくくなってしまいます。
近視の矯正方法

現在行われいる近視に対する矯正方法としてはメガネ、コンタクトレンズ、レーシックなどに代表される外科的方法などが挙げられます。また、トレーニングによって視力の回復を図る方法もありますが、効果が出るまで時間がかかる、モチベーションが続かないなどの理由であきらめてしまう方が多いようです。
眼鏡 ⇒目の乾燥を気にする必要はないので、長時間の着装が可能で、手入れもメガネを拭く程度で小さい子供でも問題なく使用することができます。
デメリットとしては、メガネがすぐに曇ってしまうことです。お風呂など危険な場所でも眼鏡をしたまま立ち入ることはできません。
また、ビジュアル的にメガネが似合わない場合もあり、近視であっても眼鏡を使用したくない人が多くいるのも事実です。
コンタクトレンズ ⇒ メリットとしてはメガネの「着装感」から解放され、裸眼のようなフィット感で食事やスポーツ、入浴などを楽しむことができます。
デメリットとしては、着装には慣れるまで長い時間が必要で、また、毎日消毒が必要であるなど面倒です。消毒などの手入れを怠ると感染症に感染したり、目を傷付けてしまい、通院が必要になるケースもあります。
また紛失してしまうケースもありその場合は、少なくない費用で買いなおさなければなりません。
レーシック ⇒施術直後は短期間ではありますが安定するまで制限や通院が必要ですが、それ以降はコンタクトレンズと同様に裸眼の状態で不自由なく日常生活を過ごす事ができます。
デメリットとしては、矯正できる近視の度数には限度があり、強度の近視や乱視の患者さんには十分な矯正が行なえないことや、矯正できる量も個人差があります。
また、矯正できるのは施術時点の視力であり、将来的な近視の進行を止めることはできません。なので年齢制限(18歳以下は施術不可)を設けている場合もあります。
クボタメガネではどうやって近視を矯正するの

クボタメガネにには製薬メーカーである「窪田製薬ホールディングス」のクボタビジョン・インク(アメリカ、ワシントン州)が独自で開発した「クボタメガネテクノロジー」を用いたウェアラブル近視デバイスです。
クボタメガネテクノロジーとは、網膜に人工的な光刺激を与えることにより、近視の進行の抑制、治療を目指す技術です。
アメリカではすでに網膜に光刺激を与えて近視の進行の抑制や治療を目指す技術は実用化されており、クーバービジョンという会社が「MiSight 1Day」というコンタクトレンズを米国食品医薬局(FDA)を受け、販売しています。
これは多焦点コンタクトレンズの仕組みを応用し、自然の光をぼかして網膜周辺に刺激を与える事で近視の進行を抑制します。
これに対し「クボタメガネテクノロジー」では、この理論的根拠をもとにナノテクノロジーを駆使してメガネに投影装置を組み込む事で自然光をぼかすことなく、直接効果的な画像を網膜周辺に投影することを実現して他の商品よりも短時間でより自然な見え方を維持しながら高い近視抑制効果を得ることを目標としています。
すでに試験段階でこのテクノロジーを使った卓上デバイスにて10人以上の治験者に対して試験を行い、世界で初めて人工的な光によって眼軸の長さが短くなったことが認められました。
具体的な形状は、プロトタイプでは丸い形をした黒縁のメガネのレンズとフレームの境目に8つの突起状のもの(LED)があり、そこからレンズ中心部にある鏡に向かって光を照射して反射した画像を網膜に映し出します。
このデバイスを1日60~90分使用することにより、近視の抑制を図るものです。将来的にはこの技術を使ったスマートコンタクトレンズも開発されるようです。
クボタ側では最初の販売は日本を含めた東アジア地域を、価格については「数十万」程度をそれぞれを想定していますが、日本においては保険適用になるかどうかも現時点では不明です。
2021年5月17日、窪田製薬ホールディングスは、近視を抑制・治療するウェアラブルデバイスである「クボタメガネ」について、医療器具として台湾当局から製造許可を取得したと発表しました。2021年度中の生産・販売を目指し、価格は日本円換算で約50万円を下回る見込みです。
まとめ
今や中・高校生の2~3人に1人は裸眼視力0,3以下で、成人の約半数が近視といわれている近視大国「日本」。
デバイスの多様化によって目を酷使することは避けられない現在、近視の抑制・治療技術は早急な進歩が望まれるものの1つだと思われます。
技術の開発が進められる一方で、各個人でも行うことのできる予防策(定期的に目を休める、マッサージをする、等)も積極的に行っていきたいですね。



